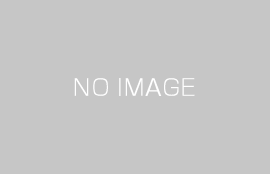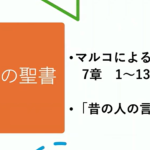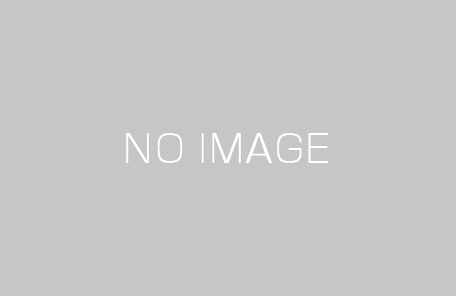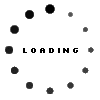先日2018年2月に亡くなった、俳優の大杉漣さんの主演作であり遺作となった「教誨師」を観ました。
この映画は、死刑囚と定期的に面談をする「教誨師」のボランティアをするキリスト教の牧師、佐伯を大杉漣が演じ、対する死刑囚の6人の一人一人との面会室での対話シーンでおそらく全体の90%以上が構成されるという、特異な映画です。にもかかわらず、最後まで緊張感が続き、牧師と死刑囚たちの深い対話、演技力に圧倒されました。
物語のなかで、牧師は当初、彼らとの対話を通して、彼らが自分の罪に向き合い、悔い改めて平安を得るようにという意図で聖書の話を伝えます。しかしその言葉は彼らの心に届かないどころか、むしろ対話の中で、牧師自身が同じ土俵へと引きずり降ろされ、内面が露わにされ、過去の罪の記憶が引き出されていく展開となっていきます。
わたしはこの映画を観ながら改めて思いました。全ての人は、いつかは死ななければならないという意味において、だれもが「死刑囚」なのだと。この主人公の牧師も、そしてこの映画をみているすべての人が、この地上を去るその日まで、一日一日をどのように生きていくのかが問われているのだと。
さて、主イエスの後に従いつつも、自分の命のことを思い悩み、不安と恐れを感じていた弟子たちに、主イエスは、「命のことで何を食べようか・・思い悩むな」「思い悩んだからといって、寿命をわずかでも延すことができようか」と諭されました。そしてむしろ「神の国を求めなさい」「・・恐れるな、あなたがの父は喜んで神の国をくださる」と天を見上げさせたのでした。自分の寿命さえどうにもできないものが、自分の思い通りにするのだと「自分の国」を求めてみても、思い悩みはつきません。人は神ではないからです。しかし人の思いや寿命さえ超え、やがて実現する「神の国」「神の支配」を求める人とは、多少自分の思い通りにならないときにも、むしろ神の思い通りになりますように祈りつつ、今日を心穏やかに生きていく術を知っている人なのです。